- 学習法
俳句とは?
基本ルールと作り方を解説
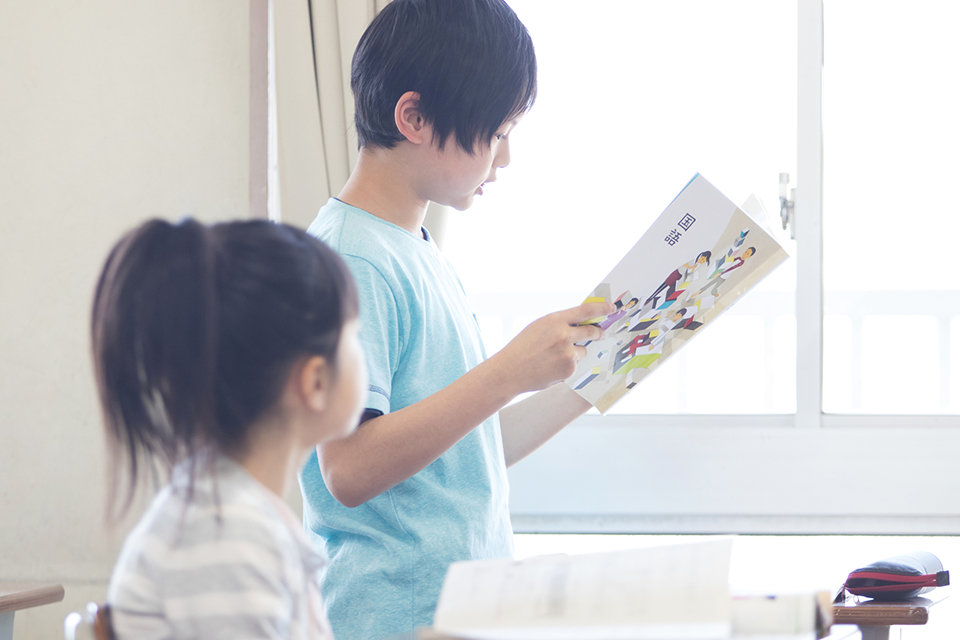
俳句は、5・7・5の17音という限られた字数の中で自由に表現できる詩の形式のことです。この短い言葉の中に、心を動かされる景色や出来事などを言い表す魅力があり、昔から多くの人に作られ、親しまれてきました。
この記事では、俳句のルールや特徴、歴史、作り方から、季語や有名な俳句までを解説していきます。
俳句の特徴と基本ルール
俳句を作るとなると、「決まった字数に季語を入れて作るのが難しい」「俳句になるような場面が思いつかない」と思う人も多いかもしれません。俳句はどのような仕組みでできているのか、その特徴やルールを見ていきましょう。
俳句とは17音の短い詩のこと
俳句は、5・7・5の17音からなる短い詩のことです。これは世界で最も短い詩ともいわれています。今から1300年前には、5・7・5・7・7の31音からなる短歌が作られており、俳句は短歌をもとにして生まれたとされています。
日本語のリズムの美しさを生かし、短い言葉で感情や情景を表現できる点が魅力で、昔から多くの人に親しまれてきました。声に出して何度も読むと、そのリズムのよさや言葉の響きを味わうことができます。
5・7・5の型と季語が基本ルール
俳句の最も大きな特徴は、5・7・5のリズムと、「季語」を入れて季節感を表現する点にあります。5・7・5の型にはそれぞれ名称があり、俳句の初めの5音を「上五(かみご)」、真ん中の7音を「中七(なかしち)」、最後の5音を「下五(しもご)」と呼びます。
また「季語」とは、俳句の中にいれる季節を表す言葉のことです。例えば、「夏の風」や「南風」という言葉が俳句に入っていれば、その俳句が夏の様子を表していることがわかります。季語は、私たちの身の回りにたくさん見つけることができ、俳句に表されている様子や景色を想像しやすくする手助けになります。さらに詳しく知りたい場合は、『歳時記(さいじき)』という季語ごとに解説や例句を載せた本を調べてみるのもいいでしょう。
「進研ゼミ小学講座」では、俳句をはじめとする国語の理解を深めるための、個別カリキュラムが充実しています。毎日コツコツ続けたくなる工夫が盛りだくさんで、お子さまが楽しみながら学習を進められるようサポートします。
俳句の作り方
俳句は、特別に感動的な場面でなくても、日常生活の中にある小さな発見やつぶやきから作ることができます。ここでは、日常における俳句の材料探しや、実際に俳句を作るための具体的な方法を紹介します。
俳句のタネを見つける
俳句を作る方法には、大きく分けて2つの型があります。1つは季語だけを使って自然の情景や季節感をそのまま表現する作り方。もう1つは、日常の出来事や感じたことをもとにして、それに合う季語を組み合わせる方法です。実際に多くの俳句は、こうした日常と季語を組み合わせる形で作られています。
日常と季語を組み合わせるときに使う「俳句のタネ」は、特別な体験でなくても、日々の生活の中での小さな発見やつぶやきで見つけることができます。例えば、日記の中から印象的な俳句のタネとして12音のフレーズを見つけたり、ふと心に浮かんだ言葉を拾い上げたりするだけでも十分です。
また、音数にこだわりすぎる必要はなく、1音多くても少なくてもかまいません。音数の数え方は、「チューリップ」で考えると覚えやすく、「チュ・ー・リ・ッ・プ」と数えて5音になります。
季語を取り合わせる
俳句作りの初心者には、12音の「俳句のタネ」に5音の季語を組み合わせ、5・7・5の型に収める型が、わかりやすくおすすめです。
例えば、「長い手紙を書きたい日」という「俳句のタネ」に、さまざまな季語を取り合わせてみます。
<同じ「俳句のタネ」にさまざまな季語を組み合わせた例>
- 「春の星 長い手紙を書きたい日」
春の夜はぼんやりとかすみ、星もかすかにしか見えない中で書く長い手紙は、新生活の報告や、なんとなく意識し始めた恋の手紙かもしれません。 - 「夏の星 長い手紙を書きたい日」
1日の中でやっと涼しくなってきた夏の夜に書く手紙は、夏休みの楽しい出来事をつづった手紙、あるいは心に抱えている思いや決意をつづった手紙、などを想像するのではないでしょうか。 - 「秋の星 長い手紙を書きたい日」
空気が澄み、星が美しく見える秋の夜は、爽やかで過ごしやすい季節。一方で、深まっていく秋とともに、物思いにふけり、別れを告げる手紙を想像する人もいるでしょう。 - 「冬の星 長い手紙を書きたい日」
冷え込み、星がさえ渡る厳しい冬の夜に書く手紙は、どうしても書かねばならない、切実な理由があるのかもしれません。
このように、取り合わせる季語によって俳句全体の雰囲気や、伝えたい情景が異なってくることがわかります。取り合わせる季語に正解はありません。また、「俳句のタネ」に近すぎない言葉を選んだほうが、よりオリジナリティのある句になります。
小学生が知っておきたい名句
ここでは、小学生が国語の授業などでふれる機会の多い、有名な俳句をいくつかご紹介します。
<小学生が知っておきたい有名な俳句>
- 雪とけて村いっぱいの子どもかな(小林一茶)
季語は「雪とけて」で雪解けを意味し、春の季語です。冬の間、雪に閉ざされていた子どもたちが、春の訪れとともに外で元気に遊ぶ様子を表しています。 - 春風や闘志いだきて丘に立つ(高浜虚子)
「春風」は春の季語です。すべてが芽吹き始める春という始まりの季節に、新たな挑戦への決意を胸に丘に立つ様子が描かれています。優しい春の風が、その決意を後押ししているかのようです。 - 名月や池をめぐりて夜もすがら(松尾芭蕉)
「名月」は秋の季語です。中秋の名月は1年で最も美しいとされ、その美しさを一晩中(夜もすがら)眺めながら池の周りを歩き、気がつけば朝になってしまったという情景を詠んだ句です。 - いくたびも雪の深さを尋ねけり(正岡子規)
「雪」は冬の季語です。雪の降る中、病床にあって自ら雪を見ることができない作者が、家族に雪の積もり具合を何度も尋ねる様子を詠んでいます。
国語への理解も自然に深まる「進研ゼミ小学講座」がおすすめ
昔から多くの人に親しまれてきた俳句。その成り立ちや作り方を知り、さまざまな言葉にアンテナを立てるようになると、語彙力が増すだけでなく、表現力を高めることができるでしょう。
「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」は、学習の積み重ねで、俳句をはじめとする国語への理解も自然と深まり、お子さま自身で毎日続けていく力が身につくように設計されています。子どもたちが小さな目標を見つけやすいように工夫されており、やる気の継続につながります。
小学生のお子さまの学習習慣を育てていきたい場合は、ぜひ、「進研ゼミ小学講座」の「チャレンジタッチ」を取り入れてみてください。
- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。















