- 学習法
音読みと訓読みの違いは?
特徴や見分け方を解説
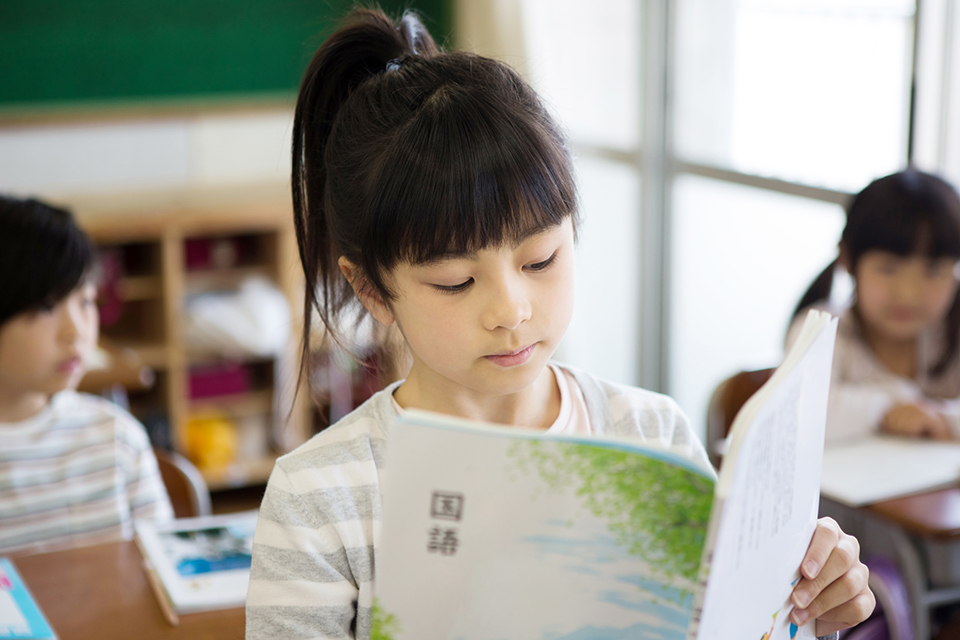
同じ漢字でもいくつもの読みがあり、それらは音読みと訓読みという2種類に分けられます。どれが音読みで、どれが訓読みなのか、判断に迷うことがあるかもしれません。
この記事では、音読みと訓読みの違いによる見分け方を紹介し、例題を通して、間違えやすい点について解説します。
<目次>
音読みと訓読みの基本を押さえよう
漢字の読み方には、音読みと訓読みの2種類があります。それぞれの由来や使い方の違いを知ることで、読み方を正しく判断することが可能です。ここでは、音読みと訓読みの意味や特徴について解説します。
音読みは大昔の中国で使われていた漢字の発音をもとにした読み方
音読みは、大昔から中国で使われていた漢字の発音をもとにした読み方です。音読みは送りがなを伴わないことが多く、単独では意味がわかりにくい場合もありますが、ほかの漢字と組み合わせた熟語になると意味がつかみやすくなります。
例えば、「草(そう)」は単体で聞くと意味がとらえにくいですが、「草原(そうげん)」や「草食(そうしょく)」のように熟語になると意味がわかります。
訓読みは日本に元々あった言葉をあてはめた読み方
訓読みは、日本に元々あった言葉を漢字にあてはめた読み方です。漢字が伝わる前は、日本には文字というものがなかったため、昔の日本人は、中国で使われていた漢字に日本語の読み方をあてはめていきました。
例えば、中国では「草」を「そう」というような発音で読んでいました。一方で、日本では茎がやわらかい植物を古くから「くさ」と呼んでいたため、「草」を「くさ」とも読むようになり、これが訓読みとなっていきます。
ほかにも、訓読みは「花(はな)」「朝(あさ)」など、聞いただけで意味がわかるものが多く、また「表す」「表れる」のように送りがなが必要になる漢字も多く見られます。
「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」なら、漢字の音読みと訓読みもお子さまが覚えやすいダジャレで楽しく学べます。まちがえた問題はその場で解説が表示され、すぐに解き直しが可能。さらに、学習履歴から苦手な問題を自動でピックアップしてくれるため、効率良くくり返し学習できます。短時間設計のレッスンで集中して取り組むことができ、お子さまが毎日続けやすい工夫が詰まっています。
音読みと訓読みの違いを例題から見てみよう
音読みと訓読みの見分け方を習ったとしても、実際にどちらの読み方なのかを判断するのは難しい場合もあるかもしれません。ここでは、例題を通して音読みと訓読みの見分け方の練習をしていきましょう。
まずは訓読みの特徴を確認
まずは、訓読みの特徴を例題で確認していきましょう。
<例題>
訓読みの特徴にあてはまる方を選びましょう。
- 訓読みは、聞いただけで意味がわかるものが多い。
- 訓読みは、聞いただけでは意味がわかりにくいものが多い。
<答え>
1. 訓読みは、聞いただけで意味がわかるものが多い。
<解説>
訓読みは日本語の意味を漢字にあてた読み方で、聞いただけで意味がわかるものが多くなっています。
同じ漢字で読み方を比べてみよう
同じ漢字の音読みと訓読みに気をつけて、次の例題の読みをそれぞれ考えてみましょう。
<例題>
太字の部分を、ひらがなにしてください。
- 歌手が歌う
- 登場人物が宝物を見つける
- 村で新しい村長が選ばれる
- 歩道をゆっくり歩く
- 火事が起こらないよう、火の扱いに気をつける
<答え>
- か/うた
- ぶつ/もの
- むら/そん
- ほ/ある
- か/ひ
<解説>
漢字の意味が単独でもわかれば訓読み、意味がつかみにくければ音読みとなっています。
- 「歌(か)」は音読み、「歌(うた)」は訓読み
- 「物(ぶつ)」は音読み、「物(もの)」は訓読み
- 「村(むら)」は訓読み、「村(そん)」は音読み
- 「歩(ほ)」は音読み、「歩(ある)く」は訓読み
- 「火(か)」は音読み、「火(ひ)」は訓読み
この読み方は音読み?訓読み?
ひとつの漢字に振られたふりがなから、この読み方は音読みか訓読みかを考えましょう。
<例題>
次の読み方は、音読みと訓読みのどちらでしょう。
- 村(そん)
- 朝(あさ)
<答え>
- 音読み
- 訓読み
<解説>
- 「そん」と聞いただけではどの意味かとらえにくいため、音読みと判断できる。
- 「朝(あさ)」は、この単語だけで意味がわかるため、訓読みとわかる。
文の中の漢字を見分けよう
同じ音読みの漢字で文章にあてはまるものや、音読みが使われている漢字の見分け方を見ていきましょう。
<例題1>
同じ「こう」という音読みの漢字で文章にあてはまるものを、A、B、Cの中から選びましょう。
家の近くにあるこう園で遊ぶ。
- 公
- 校
- 交
<答え>
A
<解説>
「公園」という単語になることから、「公」があてはまるとわかる。
<例題2>
「歩」という漢字が音読みで使われているのは、AとBのどちらでしょう。
- ゆっくりと歩く
- 歩道をわたる
<答え>
B
<解説>
「ホ」の読みについて、そのままでは意味はわかりにくく、熟語になって初めて意味がわかる読みであるため、Bが音読みとわかる。
音読みと訓読みのまちがえやすい例
音読みと訓読みは、発音だけでおおよその判断ができます。一般的に、発音を聞いて意味がわかる場合は訓読み、意味がわかりにくい場合は音読みです。
ただし、この判断方法には例外もあります。発音を聞いて意味がわかるのに音読みだったり、意味がわかりにくいのに訓読みだったりする漢字もあります。次の例は特にまちがえやすいので、注意して覚えておきましょう。
<発音で意味がわかるけれど音読み>
絵(え)、駅(えき)、客(きゃく)、図(ず)、席(せき)、線(せん)、肉(にく)、服(ふく)、本(ほん)、陸(りく)など
<発音で意味がわかりにくいけれど訓読み>
野(の)、場(ば)、日(ひ)、間(ま)、馬(ま)、身(み)、音(ね)など
苦手な教科も、くり返しわかりやすく取り組める「進研ゼミ小学講座」がおすすめ
音読みと訓読みの見分け方を知っておくと、漢字学習がより覚えやすくなります。ただし、一度理解しても時間が経つと忘れてしまうこともあるため、大切なのはくり返し練習し、知識を定着させることです。
「進研ゼミ小学講座」なら、国語や漢字の学習も一人ひとりに合わせたカリキュラムで進められます。タブレット教材「チャレンジタッチ」は、漢字の読み方を楽しいダジャレで覚えられたり、正しい書き順を映像でわかりやすく確認したりすることができます。
まちがえた直後に解き直しができるため、理解がその場で深まるのが特長です。短い時間でも集中して取り組める設計で、お子さまが毎日コツコツ続けやすい工夫がたくさん詰まっています。
家庭学習の習慣づけにもつながる「進研ゼミ小学講座」で、国語力アップを目指しましょう。
- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。















