- 学習法
中学受験の国語の勉強法は?
出題傾向や家庭学習のポイントを解説
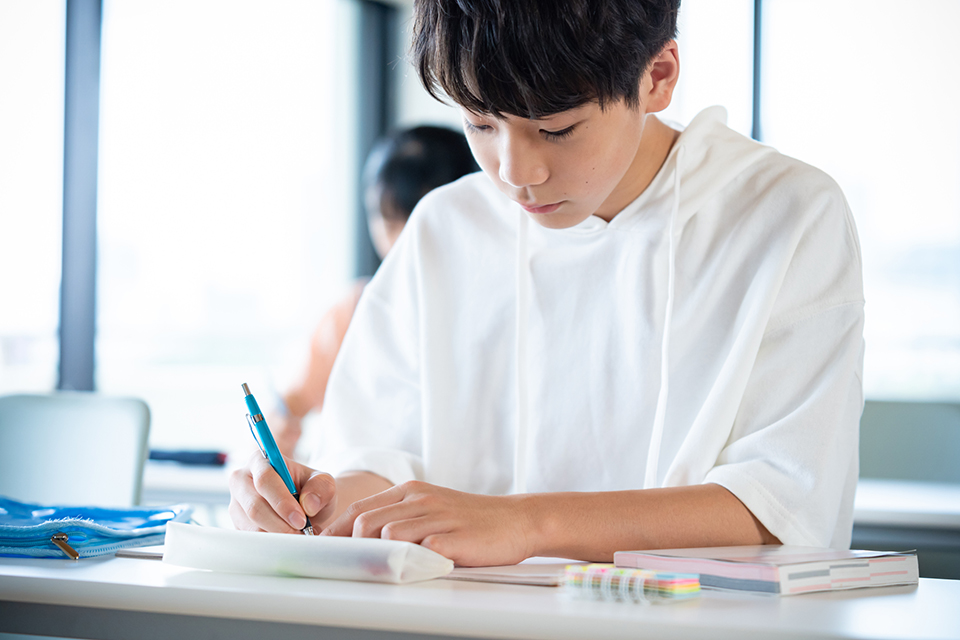
国語は中学受験の中でも「勉強方法がわからない」「対策が難しい」と悩む保護者のかたは多いでしょう。国語は暗記中心の学習が通用しにくいこともあり、感覚やセンスに左右されると思われがちですが、きちんと対策すれば得点源にできる教科です。
この記事では、中学受験の国語の出題傾向や、問題別のおすすめ勉強法のほか、家庭学習のポイントについても解説します。ご家庭での学習にぜひお役立てください。
<目次>
「国語が苦手」の勘違い
「本をたくさん読む子は国語が得意」「センスがないと国語の成績は上がらない」といった思い込みをもっている保護者のかたは少なくありません。中学受験の国語では、暗記が通用しにくく、記述問題のように答えが1つではない問題があるなど、ほかの教科とは違う独自の特性があります。そのため、つい「読書習慣やセンスが必要」と考えがちですが、実際はそうではありません。
国語の入試問題が求めているのは、文章を正しく読み取り、根拠をもって論理的に解答する力です。読解力と論理的に考える力を鍛えることで、着実に成績を伸ばせる教科だといえます。
中学受験「国語」の出題傾向
中学受験の国語では、小学校の授業では扱わないような長文が登場します。およそ2000~6000字、志望校によっては7000字を超える文章が出題されることもあります。
読解力を鍛えるためには、入試レベルの文章を使い、時間を意識しながら読む練習が効果的です。1分間に400字以上の速さで5000字程度の文章を読むことを目標にして、徐々にスピードを上げていきましょう。志望校で7000字を超える長文が出題される場合は、1分間に600~800字以上の読解力を目指すと有利になります。
出題される文章は大きく「物語文」と「説明文」に分かれます。物語文では登場人物の心情を読み取ること、説明文では筆者の主張を理解することがポイントです。
物語文を読むときは、場面の移り変わりや心情を示す表現、心情が変化するきっかけとなる出来事に注目しましょう。説明文では、「しかし」などの逆接、「つまり」とまとめる表現、「である」と断定する文末表現など、主張の肝となる部分を見逃さないことが大切です。注目した部分に線を引いて印をつける習慣を身につけると、解答の根拠探しも効率良く進められます。
中学受験「国語」のおすすめ勉強法
中学受験の国語には、選択問題・書き抜き問題・記述問題・漢字やことわざの知識問題などがあります。問題別のおすすめの勉強法を紹介します。
<中学受験「国語」の問題別おすすめ勉強法>
- 選択問題
- 書き抜き問題
- 記述問題
- 漢字、ことわざ、慣用句の問題
選択問題
選択問題は、提示された選択肢の中から最も適切なものを選ぶ問題形式です。選択問題は「なんとなく」で選ぶのではなく、論理的に根拠をもって判断することが重要です。問題演習の際には、不正解だと思う選択肢のどこが不適切なのかわかるように、印をつけて残すようにしましょう。答え合わせのときに役立つほか、根拠をもって解答する習慣も身につきます。
また、最初は時間がかかってもかまわないので、誤った選択肢を「どう直せば正解になるか」まで説明する練習をすると、より理解が深まります。
<選択問題の解き方テクニック例>
- 「あてはまるもの」「あてはまらないもの」どちらを聞かれているのか問題文を落ち着いて確認
- 本文と合致する選択肢を探すより、合致しない選択肢を探すほうが早い。「本文とは逆のこと」や「本文には書かれていないこと」が選択肢に含まれていないかチェック
- 「まったく」「必ず」「~だけ」などの断定表現がある選択肢は誤りの可能性が高い
書き抜き問題
書き抜き問題とは、本文の中から答えを抜き出して書く問題形式です。答えになるところが必ず本文の中にあります。書き抜き問題では、文章中にまちがえて選びやすい複数の候補が用意されていることを前提に取り組みましょう。まず候補に線を引いて絞り込み、そのうえで、指定された文字数と合致するものを探すという順序で考えます。
<書き抜き問題の解き方テクニック例>
- 字数のヒントから闇雲に答えを探すのは時間を浪費してしまうのでNG
- 指定の字数が多いときは、文の終わりから字数を数えると何度も数える手間が省ける
記述問題
記述問題とは、単語や短い言葉ではなく、文章で答える問題形式です。記述問題は自由度が高いように思えますが、書くべき要素は決まっています。「筆者の主張を答えなさい」と問われた場合は、本文の展開を読み解き、筆者の主張を見つけることが重要です。自分の考えを書くわけではないので、気をつけましょう。
記述問題は、答え合わせが学習効果を大きく左右します。模範解答と自分の解答を比較して、なぜその要素が必要なのか、自分の解答をどう直せば正解になるのかを考えることで、正解に必要な要素が明確になります。
<記述問題の解き方テクニック例>
- 解答欄が大きくても字数は気にしないで考える
- 問いに応じて文末を決める。理由を問われていたら「~だから」、どういうことですかと問われていたら「~ということ」など
- わからなくても空欄にせず、本文から要素を拾って書けば部分点を得られる可能性がある
漢字、ことわざ、慣用句の問題
漢字やことわざ、慣用句の知識問題は、日々の積み重ねが大切です。漢字が苦手な場合は、ドリルでくり返し書くよりも、まずはクイズ形式などで漢字に楽しくふれることから始めると、学習が習慣化しやすくなります。
例文を声に出して読むと、漢字や語彙の使い方のイメージが広がり、知識の定着にも効果的です。ことわざや慣用句は、由来を調べると記憶に残りやすいでしょう。また、短時間でも毎日継続することが大切です。
「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」なら、クイズ感覚で漢字やことわざ、慣用句の学習に楽しく取り組めるなど、お子さまが飽きずに毎日続けられる工夫があります。また、タブレットがお子さまの学習履歴から苦手な問題を自動でピックアップしてくれるため、効率良くくり返し学習できます。
中学受験「国語」のNG勉強法
「勉強しているのに成績が伸びない」という場合、誤った勉強法に時間を費やしている可能性があります。ここでは、代表的なNG勉強法を紹介します。
<中学受験「国語」のNG勉強法>
- 問題を解いて正誤だけ確認する
- わからない語句を放置してしまう
問題を解いて正誤だけを確認する
問題を解いたあと、答え合わせで正解か不正解かだけを確認して終わらせてしまうのはNGです。たまたま正解だったとしても、なぜその答えになるのかをしっかり理解できずにいると、別のときには同じような問題でまちがえてしまうなど、成績が安定しなくなります。必ず解説を読み、答えにたどり着くプロセスを確認することが大切です。
わからない語句を放置してしまう
国語の読解力を支えるのは語彙力です。問題演習中に意味のわからない語句が出てきたとき、わからないままにしてしまうと語彙力が伸びません。わからない語句に出合ったときは、辞書などで調べて、その場で確認する習慣をつけましょう。小さな積み重ねが確実に語彙力を強化し、読解力アップにつながります。
中学受験「国語」の家庭学習のポイントは?
国語の読解力は一朝一夕では身につきません。学年ごとに段階的な学習を進めることで、無理なく読解力をつけていくことができます。
低学年のうちは、まず文字にたくさんふれて「読むことへの抵抗感」をなくすことが大切です。「音読を聞いてほめる」「いっしょに本を読む」「読んだ内容を話し合う」といった家庭での働きかけが、学習の土台づくりにつながります。
4年生になったら、語彙力の強化に重点を置きましょう。短時間でも毎日こつこつと反復して取り組むことで、確実に語彙力はついていきます。長文読解の問題もこの頃から始めます。そして5年生は、長文読解のスキルを習得する時期です。志望校が決まったら、よく出題されるテーマを意識しながら、難しい文章を読み解く練習を重ねていきます。
6年生では、入試レベルの長文に対応する力を養うとともに、解答作成力を高める段階に入ります。過去問演習に取り組むことで、実践力を身につけていきます。ここまでに紹介した学年ごとの学習内容は目安なので、保護者のかたは焦らずお子さまをサポートしてください。
中学受験の国語を「苦手」から「得点源」に
中学受験の国語は、正しい方法で取り組めば得点源にできる教科です。感覚やセンスに左右されると思われがちですが、読解力や論理的に考える力を着実につけていけば、成績は伸びていきます。おすすめの勉強法を参考に取り組んでみましょう
「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、中学受験に必要な問題をくり返し学習できます。また、まちがえた問題を直後に解き直す仕組みがあり、理解をその場で深められるため、学習効率が高まり、短時間でも集中して取り組めるのが特長です。勉強法に不安があるなら、まずは無料体験で教材を試してみるのもおすすめです。中学受験に向けて「進研ゼミ小学講座」で、国語力アップを目指しましょう。
- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。















