- 学習法
小学生の英語学習にはタブレットがおすすめ!効果的な学習方法とは?
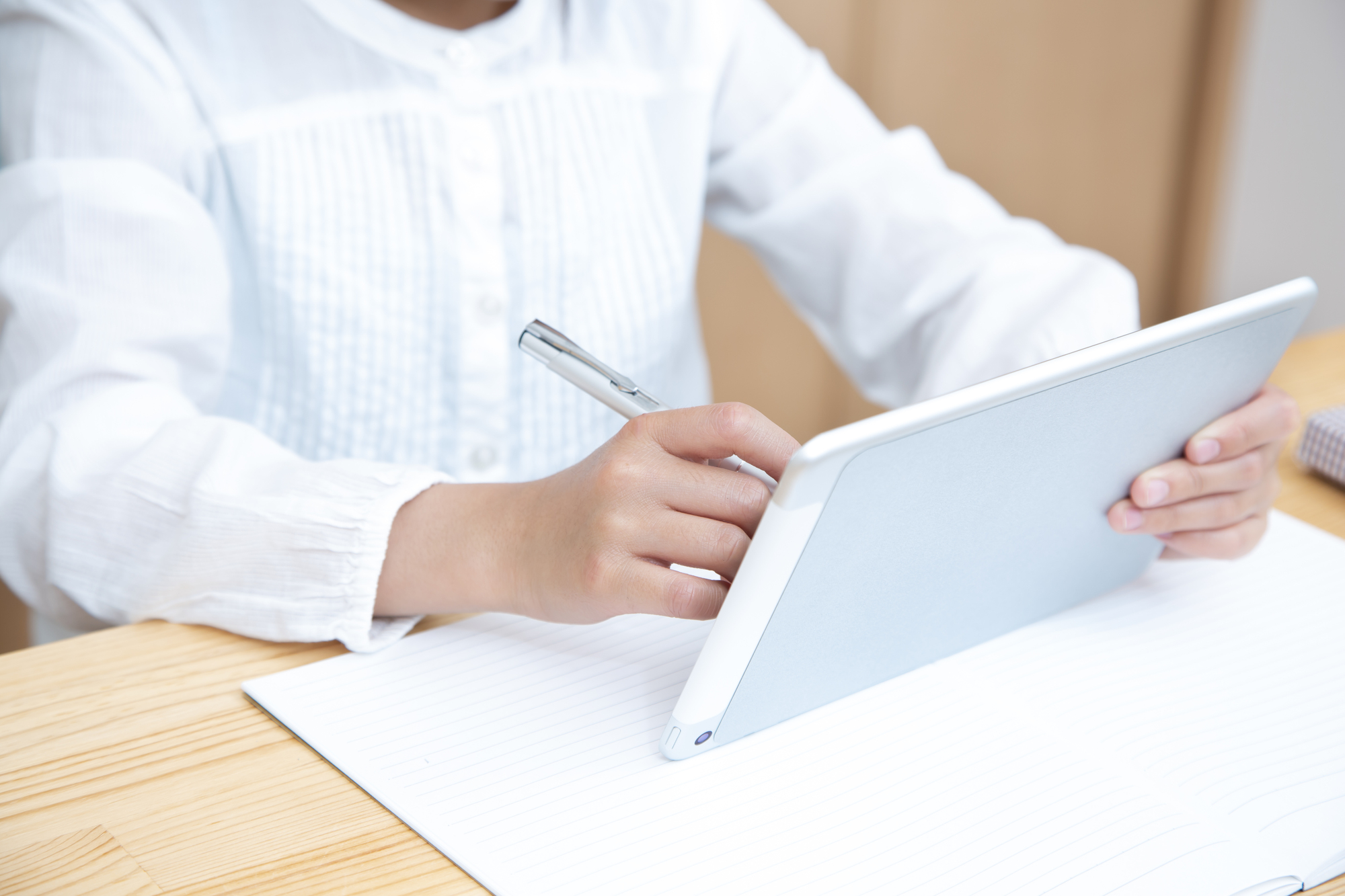
小学校での英語教育が本格化し、早いうちから英語に慣れておくことがますます重要になっています。中学に進むと英語は一気に難しくなるため、小学生のうちに「聞く・話す・読む・書く」の力を自然に身につけたいところです。
とはいえ、忙しいご家庭では毎日お子さまの学習を見てあげるのは難しいもの。そこでおすすめなのが、自宅で気軽に英語にふれられるタブレット学習です。楽しみながら英語に親しめるので、無理なく英語力を育てることができます。
この記事では、タブレット教材のメリットや効果的な使い方をご紹介します。
<目次>
現代の小学生の英語教育
小学3年生から外国語活動がスタートし、小学5年生からは英語が教科として成績評価の対象になっています。現代の英語学習がどのように行われているのかを以下で説明します。
小学3・4年生の英語
小学3・4年生の英語の授業では、歌やリズム遊び、簡単な会話を通じて、英語に楽しくふれることが中心です。この段階で最も重視されているのは、英語に“慣れる”ことです。意味を正確に理解するよりも、楽しく英語にふれること、特に会話を通じて英語の音やリズムに慣れ、話すことに抵抗感をなくしていく点が重視されています。
小学5・6年生の英語
小学5・6年生になると、英語は正式な教科として通知表で成績がつくようになります。授業では、「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく育てることが重視されており、今後の中学英語にスムーズにつなげるための基礎づくりが行われます。
英語力を育てる家庭学習のポイント
以前とは異なる英語教育に対して、「何かすべきでは」と不安になっている保護者のかたは多いかもしれません。実際に学校の授業だけでは、英語にふれる時間や量が限られているため、英語力をしっかり育てるにはご家庭でのフォローが欠かせません。
家庭学習で意識したいポイントは次の3つです。
<家庭学習のポイント>
- 英語の音にたくさんふれる
- 日常の中で簡単な英語を使ってみる
- 発音やリスニングの練習を取り入れる
こうした取り組みをサポートするツールとして、タブレット学習が注目されています。
小学生の英語学習にタブレット教材をおすすめする理由
小学生の英語学習において、タブレット教材は効果的かつ実用的な学習手段として注目されています。以下では、なぜタブレット教材が英語学習に適しているのか、その理由を詳しく解説します。
<小学生の英語学習にタブレット教材をおすすめする理由>
- 学校だけでは足りない学習量をタブレット教材で手軽に補える
- タブレットでネイティブな英語にいつでもふれられる
- AIが会話をサポートしてくれる
- ゲーム感覚で楽しめる
- タブレット1台で学習が完結する
学校だけでは足りない学習量をタブレット教材で手軽に補える
小学校の英語授業は、週1〜2回と頻度が少なく、英語にふれる量としては十分とはいえません。タブレット教材なら、毎日短時間の取り組みでも自然と英語にふれる時間を増やせるため、無理なく学習習慣をつけられます。
タブレットでネイティブな英語にいつでもふれられる
英語のリスニング力を伸ばすには、正しい発音やイントネーションをたくさん聞くことが重要です。タブレット教材では、正しい英語のリズムや音を、アニメーションや音声で自然に学ぶことができます。日本語と異なる音の構造に早いうちから慣れることで、中学以降のリスニングやスピーキングにも役立つでしょう。
AIが会話をサポートしてくれる
英語の発音は、保護者のかたが判断しにくい部分です。「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、AIキャラクターが発音をチェックし、会話形式で学べる設計になっており、AIがお子さまの発話内容を認識し、適切な返答やヒントをくれます。「自分の英語が伝わった!」という自信や意欲にもつながるでしょう。
ゲーム感覚で楽しめる
英語学習は「楽しい」と感じることが継続のカギです。タブレット教材では、アニメや音声、ゲーム要素を取り入れたレッスンなどお子さまの興味を引く構成になっているため、遊んでいる感覚で英語力を伸ばせるのもポイントです。
タブレット1台で学習が完結する
タブレット学習は、教材の準備や丸つけが不要で、タブレット1台で英語学習が完結します。さらに、AIが苦手な部分を自動判定して復習を提案するなど、親が常に学習状況を把握しなくても、お子さま自身で自立的に学習を進められる仕組みが整っています。
お悩み別|小学生の英語タブレット教材の選び方
英語のタブレット教材は多種多様で、どれを選べばよいのか迷うご家庭も少なくありません。ここでは、よくあるお悩み別に、選び方とあると便利な機能を紹介します。機能は「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」に備えている機能です。
お子さまの性格やご家庭の状況に合わせて、最適な教材を選ぶヒントにしてください。
<小学生のよくある英語学習のお悩み>
- 「英語をどう教えたらいいかわからない…」
- 「続けられるか心配…」
- 「どこまでできているか把握したい」
- 「学校の授業についていけるか不安」
お悩み1.「英語をどう教えたらいいかわからない…」
英語が苦手な保護者のかたでも、安心して使える教材を選びましょう。おすすめなのは、AIが発音の判定をしてくれたり、自動採点してくれたりする教材です。
<「チャレンジタッチ」のおすすめ機能>
- AIがお子さまの発話内容を判別し、正しい発音や表現をサポート
- ネイティブ音声で英語らしい発音に自然と慣れる
- 自動採点機能で、丸つけや解説の負担がない
お悩み2.「続けられるか心配…」
英語学習を習慣にするには、楽しく続けられる仕組みが大切です。どんなに内容が良くても、「やらされている」と感じる学習では長続きしません。毎日少しずつ無理なく取り組める教材を選ぶことが重要です。
<「チャレンジタッチ」のおすすめ機能>
- 短時間のレッスンで毎日の習慣化がしやすい
- ゲームやAIキャラクターとの会話で楽しく学べる設計
- 学習の頑張りに応じてもらえるポイントやスタンプなどのごほうび機能がやる気を継続
お悩み3.「どこまでできているか把握したい」
お子さまの進捗状況や理解度を見守れる機能があれば、保護者のかたも安心です。保護者のかたが付きっきりで見ていなくても、アプリで学習状況が確認できるので、忙しいご家庭にもぴったりです。
<「チャレンジタッチ」のおすすめ機能>
- 保護者用アプリで学習状況・理解度・履歴が確認できる
- 学習履歴や成績の通知機能付きで、見守りがしやすい
お悩み4.「学校の授業についていけるか不安」
小学校の英語は学年が上がるごとに内容が難しくなり、特に教科化される5・6年生では「成績がつく」こともあって、授業についていけるか不安になるご家庭も多いのではないでしょうか。そんなときは、教科書やカリキュラムに対応している教材を選べば、予習・復習もスムーズです。
<「チャレンジタッチ」のおすすめ機能>
- 学校の進度に沿った内容で復習・予習が可能
- つまずきポイントをAIが分析し、重点的に復習
- 必要に応じて、学年や学期をさかのぼって復習
「チャレンジタッチ」は、忙しいご家庭にこそ最適な英語学習法
小学校での英語教育は本格化し、小学3・4年生では楽しみながら慣れる段階、小学5・6年生では成績がつく教科として、英語力が問われるようになっています。しかし、学校の授業だけでは十分な英語力を育てるのは難しく、保護者自身も英語に苦手意識があったり、忙しくて勉強を見てあげられなかったりするケースもあるかもしれません。
「進研ゼミ小学生講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」は、楽しく続けられる工夫が盛りだくさんで、無理なく・楽しく・自立的に学習を進めることができます。英語に対する苦手意識を持つ前に、自然と英語を使う感覚を身につけられる環境を整えましょう。
- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。















