- 子育て・生活
勉強が苦手な子どもの原因と
やる気を引き出すサポート法を解説
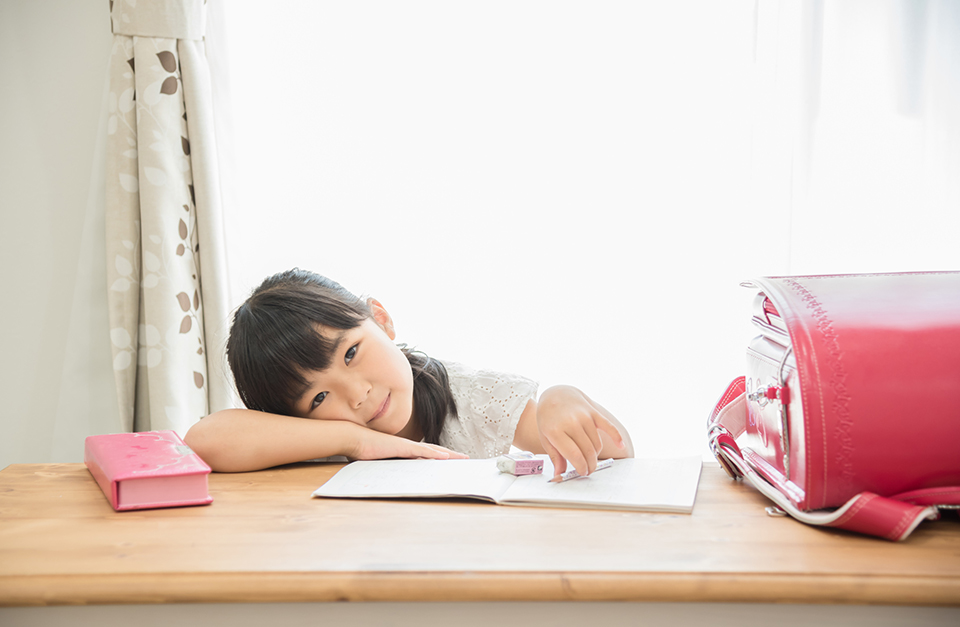
「うちの子、勉強が嫌いになっちゃったな…」と悩む保護者は少なくありません。保護者が子どものためにと思って発する言葉が、かえって子どもの意欲を削いでしまう可能性もあります。
この記事では、子どもが勉強を嫌いになる原因となるNG言動のほか、勉強習慣を身につけるコツ、保護者のサポートで注意すべきポイントなどを、詳しく解説します。お子さまの学習意欲を育てるための参考にしてください。
<目次>
子どもが勉強嫌いになる原因と改善アプローチ
子どもが勉強嫌いになる原因として、保護者の特定の言動が背景にあるかもしれません。ここでは、子どもが勉強嫌いになる保護者の主な4つのNG言動と、改善するためのアプローチを詳しく紹介します。
<子どもが勉強嫌いになる保護者の主なNG言動>
- 「早くしなさい」などの曖昧な指示
- 「どうしてわからないの?」などの詰問・否定
- 長すぎる説明
- 努力や成功の見逃し
「早くしなさい」などの曖昧な指示
「早くしなさい」「ちゃんとやりなさい」といった抽象的な言葉は、子どもには伝わりません。曖昧な指示では子どもはどうすればいいのかが具体的にわからず、戸惑ってしまいます。
こうしたケースでは、「15分でこのページを終わらせよう」と具体的な時間まで伝えるなど、具体的な内容にまで落とし込んで指示することが大切です。
例えば、「丁寧にやりなさい」であれば「漢字はトメ・ハネまできちんと書こう」、「見直ししなさい」であれば「まず解き忘れがないかチェックしよう」「次に自信がない問題を確認するといいよ」など、順番や見るべきポイントを具体的に伝えるようにしましょう。
「どうしてわからないの?」などの詰問・否定
子どもが簡単な問題を間違えたり、解き方がわからず手をつけられなかったりする様子を見たとき、つい「なんでわからないの!」と詰問してしまうこともあるかもしれません。しかし、こうした詰問や否定は、子どもは責められている、叱られていると感じ、自己肯定感を傷つけてしまいます。
また、「どこがわからないの」と尋ねるのも注意が必要です。子ども自身がどこまで理解し、どこからわからないのかを言葉で説明するのはとても難しいからです。
こうしたケースでは、「どこからわからなくなったのかいっしょに見てみよう!」と声をかけ、つまずきの箇所をいっしょに探すサポートをしましょう。責めるのではなく、寄り添う姿勢が重要です。
長すぎる説明
子どもの「わからない」をサポートしようとして、おうちのかたがくどくどと説明をすることがあるかもしれません。しかし、長すぎる説明は子どもの理解を阻害してしまう可能性があるため、注意が必要です。子どもは一度に大量の情報を処理できず、情報量が多すぎると何を説明されているのかがわからなくなってしまうからです。
子どもが一度に理解できることは1つか2つです。子どもが1つ理解できたら次の説明に移るという「スモールステップ式解説」を心掛け、子どものペースに合わせて説明してください。子どもの理解度を確認しながら、段階的に進めることが効果的です。
努力や成功の見逃し
子どもができなかったり、わからなかったりする箇所ばかりを指摘し、できたときには当たり前のように見逃してしまうケースも、子どものやる気を奪っています。大人にとっては「できて当たり前」と思える問題でも、子どもにとってはハードルが高いことも多いものです。せっかく苦労して取り組んだのにスルーされてしまったら、子どものモチベーションが下がりかねません。
この場合は、「できたね、すごい!」「時間通りにできてる!やったね!」など、子どもの努力や成功をまずは受け止め、褒める言葉をかけてあげてください。努力を認めてもらう経験が、子どもの勉強への意欲向上につながります。
子どものやる気を引き出す!保護者の関わり方10選
子どもの勉強へのやる気を高めるために、おうちのかたができることは多くあります。ここでは、子どもの学習意欲を高める保護者の関わり方を、10のポイントで紹介します。ぜひ実践してみてください。
<子どものやる気を引き出す保護者の関わり方10選>
- 集中できる環境をつくる:机には勉強に必要なものだけを置き、集中できる環境をつくる
- 体験学習で学びと世界をつなぐ:虫取りなど、実際に体験させ、教科書の知識とつなげる
- 規則正しい生活リズムを整える:適切な睡眠と食事で集中力が高まり、やる気が継続する
- 保護者が学ぶ姿勢を見せる:身近な大人が常に学ぶ姿勢を見せれば、学びが当たり前のことになる
- ポジティブな声かけを心掛ける:意識的にポジティブな言葉を使うと、挑戦したりやる気を出したりする気持ちを育てられる
- ほかの子と比べない:その子ども自身の成長に焦点を当て、努力を褒めるとやる気が育つ
- いっしょに勉強の計画を立てる:子どもだけで計画を立てることは難しいので、いっしょに無理のないスケジュールを組む
- 「なぜ勉強するか」を伝える:勉強の意味や価値を伝えると、自発的な学習意欲が生まれやすくなる
- 読書の習慣を育てる:語彙力や読解力、想像力が育ち、知らない世界を広げる喜びにつながる
- 遊びの中で学ぶ機会を作る:社会経験や体験学習、自然の中での遊びが勉強の理解を深める
勉強習慣を身につける6つのコツ
小学生が勉強習慣を身につけるためには、「勉強しなさい」と言うだけでは不十分です。まずは短時間でも毎日続けられることを優先し、以下の6つのポイントを意識して習慣づくりに取り組みましょう。
<勉強習慣を身につける6つのコツ>
- 小さな目標を立てる
- 計画を立てて可視化する
- 時間・場所を固定してルーティン化する
- 振り返りと修正の時間を持つ
- 結果でなく過程を認める声かけをする
- 家族で勉強タイムを設ける
1. 小さな目標を立てる
「勉強したい」という気持ちを高めるには、達成感を味わうことが不可欠です。最初は「いつまでにドリルを終わらせる」や「次のテストで◯点以上を目指す」など、無理のない小さな目標から始め、少しずつハードルを上げていくと、挑戦して達成する楽しさから勉強するようになります。大きすぎる目標は挫折の原因となるため、確実に達成できる小さな目標の設定が重要です。
2. 計画を立てて可視化する
習慣化には計画が欠かせません。目標とセットで計画を立てると、「この日までにこれを終わらせる」「だから今日はこれに取り組む」というように、行動につながります。目標を計画に、計画を行動に、そして行動を習慣へとスムーズにつなげていきましょう。カレンダーやチェックシートを活用して、進捗を見える形にすることも効果的です。
3. 時間・場所を固定してルーティン化する
勉強も、する時間やタイミングを決めてルーティン化すれば習慣が身につきます。例えば歯磨きのような習慣は、行う時間やタイミングが決まっていることが多いものです。勉強も同様に、「夕食後の30分」「寝る前の15分」など、決まった時間に勉強する習慣をつけると、自然と勉強モードに入れるようになります。
4. 振り返りと修正の時間を持つ
目標や計画を振り返り、修正していく時間を確保しましょう。計画どおりに進めば達成感を得て次の計画を立てる意欲が高まります。計画どおりに進んでいない場合は、原因を考え軌道修正すれば、「もう一度やってみよう」と気持ちを新たにできます。週に一度程度、親子で振り返りの時間を設けることをおすすめします。
5. 結果でなく過程を認める声かけをする
勉強を習慣化するには達成感が大切であり、これは保護者から認められたり褒められたりすることでも高まります。テストの点数ばかり褒めてしまうのは逆効果になりかねないため、「今日も勉強できたね」「集中してがんばっていたね」「前に間違えた問題も解けるようになったね」のように、結果だけでなく過程そのものを評価する声かけをしましょう。これにより、努力することに対して前向きになれます。
6. 家族で勉強タイムを設ける
家族で勉強する時間を作ると、保護者をお手本として、子どもにとって勉強が当たり前に感じられるようになります。きょうだいや親子で勉強する時間を作ると、子どもの気が散らなくなるメリットもあります。保護者が本を読んだり、調べ物をしたりと、学ぶ姿を見せると、勉強の大切さを学ぶきっかけにもなるでしょう。
おうちでの学習習慣を身につけるためには、「進研ゼミ小学講座」の「チャレンジタッチ」がおすすめです。1回7~15分の集中学習で、楽しみながら勉強が好きになれます。今日やることは「チャレンジタッチ」が決めてくれるのでお子さまが1人で始められ、理解度に合わせた徹底個別おさらいで効果的に学習できます。やる気を引き出す仕組みがたくさんあるので、ぜひ一度お試しください。
保護者のサポートで注意すべきポイント4つ
おうちのかたがお子さまの勉強をサポートする際には、以下の4つのポイントに気をつけながら、適切なサポートを心掛けてください。
<保護者のサポートで注意すべきポイント4つ>
- 口出ししすぎない
- 強制しない
- 集中できる環境を整える
- 時間より内容で目標を設定する
1. 口出ししすぎない
おうちのかたに口出しされすぎてしまうと、お子さまはやる気がなくなります。大人にも覚えがあるように、あまりに口出しされると急にやる気がなくなることは、小学生にもよくあります。
まずは優しい声かけから始めて、子どもの様子を見るようにしましょう。子どもが自分で考え、行動する機会を奪わないよう注意が必要です。
2. 強制しない
無理やり勉強させても、勉強に対して悪いイメージがついてしまい、習慣化にはつながりません。無理やりやらされると、強制されて勉強していることになり、子どもは進んで勉強したくなくなってしまいます。子どもがみずから気づき、進んで勉強するまである程度待ってみるのも一案です。
3. 集中できる環境を整える
子どもにとって勉強に取り組みやすい環境を整えることも重要です。特に小学生は気が散りやすく、視界に好きなものが入るだけで気を取られて集中できなくなります。
机の周りにゲームやマンガなどの娯楽を置かないようにし、テレビを消すなど、勉強に集中できる環境を作ってください。
4. 時間より内容で目標を設定する
勉強の効果を高めるためには、「算数の割合の復習として、週末は問題集の◯ページをやってみる」といった具合に、勉強する内容と期限をセットで決めるようにしましょう。「1日1時間は勉強しなさい」など、勉強時間の「長さ」にこだわらず、目的意識を持って勉強に取り組む姿勢を育めば、学習がより習慣化しやすくなります。
勉強が苦手なお子さまには「進研ゼミ小学講座」の「チャレンジタッチ」がおすすめ
子どもが勉強嫌いになるのは、勉強する環境やおうちのかたの声かけ、あるいは勉強方法のどれかが合っていないサインといえます。
まずは、お子さまができたことや努力をしっかりと褒めて、学習環境を整え、おうちのかたもいっしょに「できたね」「がんばったね」と子どもの努力や成長を楽しむ姿勢で関わると、子どもの学習意欲を高め、主体的な学びへとつながるでしょう。
「進研ゼミ小学講座」の「チャレンジタッチ」は、お子さまの興味・関心をひきつける工夫と、忙しいおうちのかたを支える機能が満載です。勉強への苦手意識を克服し、理解できる楽しさを実感するためにも、「チャレンジタッチ」から学習習慣につなげてみてはいかがでしょうか。
- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。















